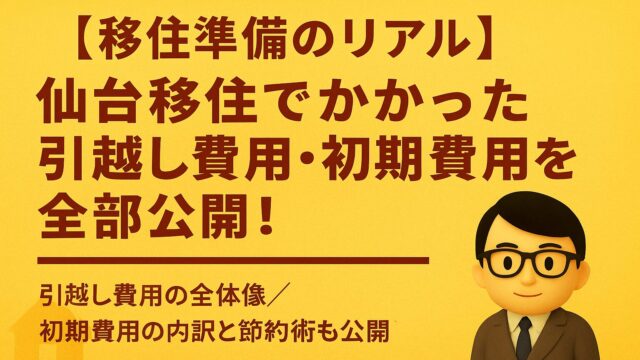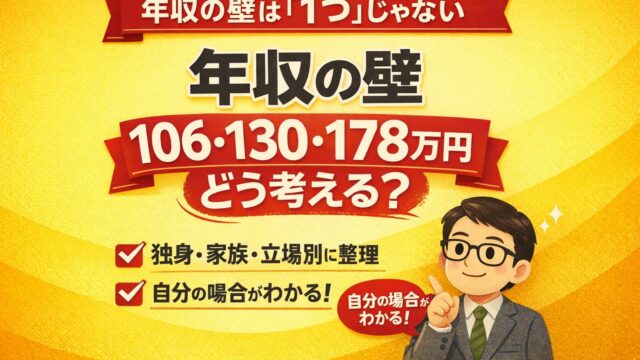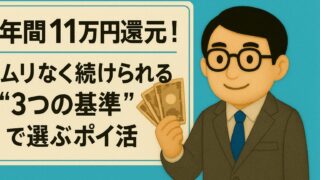一部リンクはアフィリエイトを利用しています。商品・サービスの選定は実体験に基づき、正確な情報提供を心がけています。

はじめに|育休は“お金と暮らし”のリセット期間
「育休を取りたいけど、収入やキャリアが心配…」そんな不安から一歩踏み出せずにいる方へ。私は30代の会社員として、共働き家庭の中で産後パパ育休を含めて4.5ヶ月間の育児休業を取得しました。
最初の1.5ヶ月は妻と協力してミルクや寝かしつけ、家事を分担。その後、娘と2人で過ごした2ヶ月間は、まさに“擬似FIRE”のような時間。自分の時間は限られ、生活リズムは子ども中心。でもその中で得た「暮らしの見直し」と「時間の価値」は、サイドFIREを目指す上でとても貴重な経験となりました。
この記事では、私の育休中のスケジュールや家計管理、そして**2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」**の最新情報まで、わかりやすく解説します。
- 父親が育休をとるメリットと注意点
- 父親が育休をとって実際に感じたこと
- 育休中の過ごし方
育休中の1日の過ごし方|4.5ヶ月育休を取った実体験

【体験談】妻と2人で取った育休と交代で取った育休がある
私はまず、新設されたパパ育休を利用して4週間の育休と通常の有給を合わせて1.5か月取りました。その後、妻が仕事復帰してから娘の保育園が始まるまでの期間に通常の育休で3ヶ月、合わせて4.5ヶ月ほど育休を取りました。最後の1ヶ月は慣らし保育期間だったので大きく、
- 妻と一緒に取った育休(娘0ヶ月から1ヶ月)
- 娘と2人で過ごした2ヶ月(娘4-6ヶ月)
- 娘と2人で過ごした慣らし保育期間1ヶ月(6-7ヶ月)
に分けられます。この章では前提となるそれぞれの期間の1日の流れを書かせていただきます。生後5ヶ月くらいからは離乳食が始まるので少し家事が増えますが、基本的には娘の昼寝時間に合わせた3時間サイクルくらいで生活していました。
基本的にこの方針で育休をとったことに満足していますが、妻とは2人で取って子育てをする時間があれば、娘の成長をお互いに感じられて良かったかもとたまに話をしています。
妻と一緒に取った育休(娘0ヶ月から1.5ヶ月)
- 3時間置きにミルクと寝かしつけ
- 3時間の間に家事 ※妻の実家にお世話になったので家事は一部
娘と2人で過ごしていた2ヶ月(娘4-6ヶ月)
- 4時にミルクと寝かしつけ
- 7時に起床後、1時間30分程度一緒に遊ぶ1&昼寝30分から2時間の繰り返し
- 4時間置きにミルク
- 19時にお風呂、その後ミルクを飲み、20時前後に就寝
- 5ヶ月から10時に離乳食(1回食)を開始
慣らし保育期間1ヶ月(6-7ヶ月)
- 6時にミルクと寝かしつけ
- 8時30分に起床後、9時に保育園に登園
- 16時30分まで慣らし保育 ※1時間保育から2日毎に1時間程度保育時間を伸ばす
- 18時にミルク
- 19時にお風呂に入り、ミルクを飲み、20時頃に就寝
- 離乳食は2回食(10時と14時)
サイドFIREの視点で見た育休の価値
育休中は一時的に収入がなくなるので「生活の満足度と支出のバランス」を見直す機会にもなりました。時間もあり、「本当に必要な支出は何か」「無くても困らないサービスは何か」を考えることができたので、支出の見直しができました。
また、仕事がないので時間の主導権が自分にある暮らしになります。「何に時間を使いたいのか」を自分に問い直すようにもなりました。これは、資産額だけでなく“納得感ある時間の使い方”を重視するサイドFIREにおいて、非常に重要な視点だと感じています。
一番実感したのが、
- 仕事があるから家事ができない
- 仕事があるからこの辺りにしか住めない
- 仕事があるから~できない
といつの間にか仕事の優先順位が生活より高くなっていること。仕事は私がいなくても進んでいきます。ただ、私は私の生活が1番であり、その1つが仕事であるはずです。
- このような生活がしたいからこの仕事をする
- このような生活がしたいからこの辺りに住む
と考えをしっかり持たなければいけないと感じました。
また、共働きでしたが、どちらかだけ働く生活は家族と幸せな時間が取れる。働いていない方は余裕を持って家族を支えられるので、けんかも減ると感じました。
- 収入が減った際の実感ができる:投資や節約の見直しに直結
- 自分が主役の暮らし:FIRE後の生活シミュレーション
- 家族との幸せな時間:お金よりも価値のある体験
2025年版|育休中に受け取れる主な給付制度

この章では、育休中に受け取れる代表的な3つの給付制度と注意点ついて解説します。
育児休業給付金
- 雇用保険加入者が対象
- 最初の6ヶ月:賃金の67%、その後は50%
- 非課税かつ社会保険料免除 → 手取りは約80%
出生時育児休業(産後パパ育休)
- 出生後8週間以内に最大4週間(2回に分割可能)
▶ 育児休業給付金と出生時育児給付金の詳しい条件・申請の流れ・注意点などは、こちらの記事にて解説しています。
【2025年新制度】出生後休業支援給付金
2025年4月から新たにスタートした制度で、従来の育児休業給付金に加えて支給される“上乗せ型”の給付金です。私が利用した2022年にはなかったのでうらやましいです。
- 目的:男女ともに育休を取りやすくし、共働き育児を支援するための制度。
- 対象者:本人および配偶者がそれぞれ14日以上の育休を取得すること。
- ただし、配偶者が無職・自営業・育休取得不可などの事情がある場合も柔軟に対応されます。
- 支給額:休業開始時賃金日額 × 最大28日 × 13%
- 例:賃金日額が1万円の場合 → 1万円 × 28日 × 13% = 約36,400円
- 給付条件の補足:出生時育児休業または通常の育児休業を通算して14日以上取得していることが要件。
- 他制度との併用:育児休業給付金・出生時育児休業と併用可能。実質的に“手取り100%”に近づく設計です。
- 非課税・社会保険料免除:給付金は非課税であり、社会保険料も免除されるため、金額以上のメリットがあります。
- 対象:本人および配偶者が14日以上の育休を取得(例外あり)
- 金額:賃金日額 × 最大28日 × 13%
- 他の給付金と併用可能 → 実質手取り100%も可能
- 社会保険料免除、非課税のため非常に有利
自治体の支援制度
- 東京都港区「父親育休支援金(月10万円)」など自治体の支援制度がある可能性もあるのでご自身の住んでいる自治体の制度を必ずご確認ください。
注意点|育休前に“+1ヶ月分の現金”を用意
私が育休で一番驚いたのは、「給付金が遅れて振り込まれる」ことでした。2か月後くらいに振り込まれると思っていたのですが
- 給付金の申請は育休終了後まとめて行うケースが多く、実際に手当が振り込まれたのは育休終了間際。
- 給料という定期収入がなくなり、前の月の社会保険料や税金で毎月収支がマイナスになる。
- 妻の場合は、産休前の最後の月に産休中の保険料や税金を支払っていました。
また、慣らし保育が始まると月謝+保育園準備品の出費が急増。 特に驚いたのは「着替えの多さ」。毎日複数枚必要なので、洋服の買い足しが想定以上にかさみました。
→ 育休期間+1ヶ月分の生活費と突発費用を現金で確保することを強くおすすめします。
▶ こちらの記事にて給付金の計算方法や育休中の社会保険料や税金についても解説しているのでぜひ参考にしてください
まとめ|育休はサイドFIREの“予行演習”

「収入が減っても暮らせる感覚」「家族との時間の大切さ」「時間にゆとりのある生活の豊かさ」──これらはすべて、サイドFIREに通じる価値です。
新制度「出生後休業支援給付金」をはじめ、育休を取りやすくする環境が整ってきた今、迷っている方はぜひ育休をとって欲しいと心から思います。
育休はキャリアの“後退”ではなく、人生設計の“前進”になる──私の実感です。