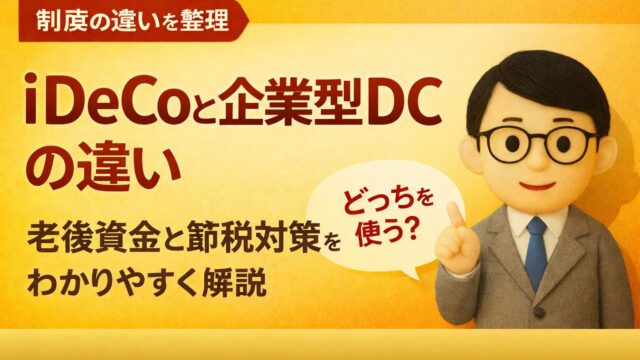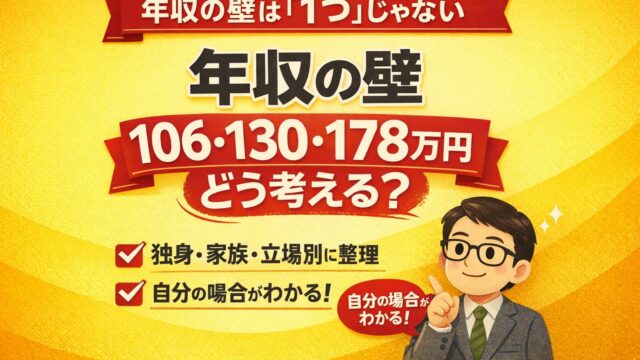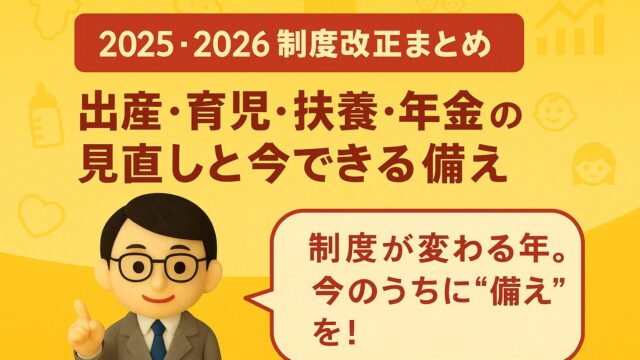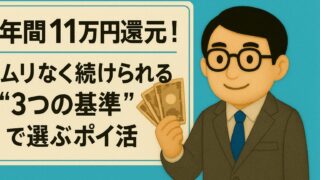一部リンクはアフィリエイトを利用しています。商品・サービスの選定は実体験に基づき、正確な情報提供を心がけています。

「もしも自分に何かあったら…」「病気で働けなくなったらどうしよう…」
子育て中の家庭やこれからの人生を見直したい人にとって、“万が一の備え”はとても大切です。
そんなときに支えとなるのが、遺族年金と障害年金。
どちらも国の公的年金制度ですが、受け取れる条件や金額、対象となる人には違いがあります。
特に2025年の制度改正では、遺族年金の支給期間が「終身」から「原則5年の有期給付」に変わるなど、大きな変更も。
知らずに申請漏れすると、受け取れるはずの年金が“ゼロ”になる可能性もあります。
本記事では、
- ✅ 遺族年金と障害年金の違いと共通点
- ✅ 支給される条件と金額の目安
- ✅ 2025年の法改正でどう変わったのか?
- ✅ 制度をうまく活用するための注意点
を、家族の視点からわかりやすくまとめました。
「制度が複雑でよくわからない…」という方でも安心して読めるよう、
具体的な支給例・よくある疑問・最新の改正情報までやさしく解説していきます。
👉他の制度も気になる方はこちら

👉筆者について気になる方はこちら

🟦 遺族年金とは?|家族を支える生活保障制度
家族の大黒柱が亡くなったときに、残された配偶者や子どもの生活を守るために支給されるのが遺族年金です。大きく分けて2種類あり、それぞれ支給対象や金額、支給期間が異なります。
- ✅ 遺族基礎年金(国民年金加入者などが対象)
- ✅ 遺族厚生年金(厚生年金加入者が対象)
次からそれぞれの支給額の目安を紹介いたします。
🔷 遺族基礎年金の概要と計算方法

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 18歳までの子がいる配偶者 または 子本人 |
| 条件 | 亡くなった方が国民年金の加入者(または資格期間あり) |
| 支給額(2025年) | 年額 793,300円+子の加算 ・第1子・第2子 各228,700円 ・第3子以降 各76,200円 |
| 支給期間 | 子が18歳の年度末まで(障害がある場合は20歳まで) |
この表から計算すると子どもが2人いれば、年額 約1,250,000円程度が支給されます。
🔷 遺族厚生年金の概要と計算方法

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母など(受給順位あり) |
| 支給条件 | 亡くなった方が厚生年金加入中、または一定の加入期間を満たしていた場合 |
| 支給額 | 報酬比例部分の 4分の3 |
| 支給期間 | 原則:終身(※下記「制度改正」により今後変更予定) |
遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の「平均標準報酬月額」と「加入期間」によって変わります。以下の計算式で年額が算出されます。
🔹 計算式:
コピーする編集する報酬比例部分(年額) =
平均標準報酬月額 × 5.481 ÷ 1,000 × 被保険者期間(月) ÷ 12
この金額に3/4をかけた金額が、実際の支給額です。
📘 計算例
- 平均標準報酬月額:30万円
- 被保険者期間:120ヶ月(10年)
年額:30万円 × 5.481 ÷ 1,000 × 120 ÷ 12 = 約164,430円
実支給額:その3/4 → 約123,322円/年
※ 遺族基礎年金と併給されるケース(子のある配偶者など)では、基礎年金分に子の加算(1人あたり年額228,700円)が付くため、年額35万円前後になることもあります。
🆕 2025年の制度改正ポイント

2025年に成立した年金制度改正により、遺族厚生年金の仕組みは今後大きく見直される予定 です。以下は「方向性」であり、実際の適用時期や対象は 段階的に施行 されます。
| 改正項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給期間 | 原則「5年間の有期給付」へ見直し予定 |
| 継続給付 | 障害状態・収入状況・子の扶養状況など、一定条件を満たす場合は延長あり |
| 所得要件 | 従来の年収850万円基準は見直し・緩和の方向 |
| 中高齢寡婦加算 | 廃止予定 |
| 新制度 | 「死亡時分割制度」を創設予定 |
| 年金額改定 | 2025年4月より 1.9%引き上げ (※制度改正ではなく物価・賃金スライドによるもの) |
この改正で支給期間を整理すると以下のようになります。
| 年金の種類 | 支給期間 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子が18歳到達年度末まで(障害のある子は20歳まで) |
| 遺族厚生年金 | 原則5年間(※今後の制度改正で導入予定/延長条件あり) |
また、延長が想定されるのは以下のようなケースです。
- 受給者が 障害等級に該当 する場合
- 就労収入が一定基準以下の場合(基準は今後の制度運用で判断)
- 子を引き続き扶養している場合
💡 こんなときどうなる?
Q. 子どもがいる専業主婦が夫を亡くした場合は?
→ 遺族基礎年金+遺族厚生年金の 併給対象。子の加算もあり、一定の生活保障が確保されます。
Q. 子どもがいない会社員の妻が亡くなった場合は?
→ 制度改正により、性別による不利な扱いは解消され、夫も遺族厚生年金の受給対象となる方向 です。
🔎 補足(重要)
※ 本パートは 2025年時点の制度と、成立済みの改正内容をもとに整理 しています。
※ 実際の適用開始時期・対象者の詳細は、今後の政省令で確定します。
🟦 障害年金とは?|病気やケガで働けなくなったときの生活保障

障害年金は、病気やケガなどで生活や仕事に支障が出る状態になったときに支給される「本人向けの生活保障制度」です。
公的年金制度の一部であり、加入していた年金の種類に応じて、
- ✅ 障害基礎年金(国民年金加入者など)
- ✅ 障害厚生年金(厚生年金加入者)
のいずれか、または両方が支給されます。次からそれぞれの詳細を紹介します。
🔷 支給の対象となる人

以下のようなケースでも支給対象になる可能性があります。
- 働いている途中で うつ病や双極性障害など精神疾患を発症した
- がんや糖尿病、脳卒中、心疾患による障害が残った
- 子ども時代に病気になった(20歳前障害)
💡 必ずしも「重度障害」だけが対象ではなく、日常生活や仕事に制限がある状態であれば、初診日や書類がそろえば支給される可能性があります。
🔶 支給要件(3つのポイント)
要件 | 内容 |
|---|---|
| 初診日要件 | 原因となった病気・けがの初診日が 公的年金に加入している期間内であること |
| 納付要件 | 初診日の前日時点で 「2/3以上の納付」または「直近1年に未納なし」 |
| 障害等級要件 | 障害認定日に、所定の障害等級(1〜3級)に該当していること |
🧾 等級と支給される年金の種類
| 障害等級 | 支給される年金 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 1級 | 障害基礎年金 or 障害厚生年金 | 日常生活のほぼ全てに介助が必要な状態 |
| 2級 | 同上 | 日常生活に大きな制限がある |
| 3級(厚生年金のみ) | 障害厚生年金 | 軽度の障害であっても労働に制限がある状態 |
🔸障害等級の判定は、病気やけがの種類に応じた「障害認定基準」に基づいて、医師の診断書で審査されます。
💴 支給額の目安(2025年時点)
障害基礎年金(1・2級のみ)
| 等級 | 年額(2025年) |
|---|---|
| 1級 | 992,100円 × 1.25 ≒ 約1,240,000円 |
| 2級 | 992,100円 |
※ 子の加算あり(第1・第2子 各228,700円)
障害厚生年金(1〜3級)
障害厚生年金は、加入期間・報酬額・等級により金額が変わります。
報酬比例部分の計算式は以下の通り:
コピーする編集する報酬比例部分 = 平均標準報酬月額 × 5.481 ÷ 1,000 × 加入月数 ÷ 12
- 1級:上記の1.25倍
- 2級:上記の金額
- 3級:最低保障額(年額 607,100円)あり
✅ 厚生年金加入者は、基礎年金と併せて受給できることもあります。
⏳ 支給期間と更新
- 原則として、障害状態が継続する限り支給されます(終身ではなく“更新制”)
- 多くの場合、1〜5年ごとに「診断書(障害状態確認届)」の提出が必要
🔎 支給停止になった場合でも、状態が悪化すれば再申請が可能です。
💡 よくある誤解
- 「病名で判断される」と思われがちですが、実際は**“状態の重さ”が基準**です
- 通院中でも、初診日が特定できないと申請ができません
🟪 遺族年金と障害年金の共通点と違いまとめ
ここまでご紹介した「遺族年金」と「障害年金」は、どちらも公的年金制度の一部として用意された生活保障制度です。
ただし、対象となる人・支給条件・受給期間などに違いがあり、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
🔍 一覧で比較!遺族年金と障害年金の違い
| 比較項目 | 遺族年金 | 障害年金 |
|---|---|---|
| 主な対象者 | 残された遺族 (配偶者・子など) | 本人 (病気やけがで障害状態) |
| 給付の目的 | 遺族の生活を支える | 障害状態となった本人の生活保障 |
| 支給される年金の種類 | 遺族基礎年金/遺族厚生年金 | 障害基礎年金/障害厚生年金 |
| 支給の条件 | 死亡時に年金加入中 or 資格あり | 初診日が年金加入中+ 障害等級該当 |
| 納付要件 | 加入期間の2/3以上納付 など | 同左(初診日の前日時点) |
| 支給期間 | 原則5年(遺族厚生年金) ※条件により延長あり | 障害状態が継続する限り ※定期的に更新あり |
| 子の加算 | あり(遺族基礎年金) | あり(障害基礎年金) |
| 手続きの流れ | 死亡診断書+戸籍書類などを提出 | 初診証明+診断書などを提出 |
| 併給の可否 | 原則不可(※一部例外あり) | 原則不可(※一部例外あり) |
✅ 共通点
- どちらも国の年金制度(国民年金・厚生年金)から支給
- 自己申請が必要(申請しないともらえない)
- 納付要件や申請書類に注意が必要
- 子がいる場合には「加算」があり、家族の生活保障として役立つ
⚠ 注意点:併給できるケースもある?
原則として、遺族年金と障害年金は同時には受け取れません(併給不可)。
ただし、以下のような一部例外的な併給パターンは認められています。
| パターン | 可能な組合せ |
|---|---|
| 配偶者が障害者で、配偶者が亡くなった | 障害基礎年金+遺族厚生年金 |
| 子どもが障害者で、親が亡くなった | 遺族基礎年金+ 障害年金の切り替えが必要な場合あり |
✅ 実際に併給できるかどうかは、個別のケースで判断されるため、年金事務所や専門機関での相談が安心です。
💬 遺族年金・障害年金に関するよくある質問(Q&A)
制度は聞いたことがあるけれど、実際の申請や金額には不安が多いもの。
ここでは、読者からよく寄せられる疑問や誤解をQ&A形式で解説します。
❓Q1. どちらも該当する場合、両方もらえるの?
🅰 原則として、遺族年金と障害年金の同時受給(併給)はできません。
ただし、例外として以下のパターンでは一部の年金を組み合わせて受け取ることが可能です。
- 障害基礎年金+遺族厚生年金(※配偶者が障害者だった場合など)
- いずれかを選択して「より有利な制度」を選ぶことも可能
✅ 自分のケースが該当するかは、年金事務所で確認を。
❓Q2. 子どもがいると年金が増えるって本当?
🅰 はい、本当です。
- 遺族基礎年金では、**18歳までの子どもに加算(1人あたり約22万8,700円/2025年時点)**があります。
- 障害基礎年金にも、子の加算があります(第1・第2子 各22万8,700円、第3子以降は7万6,200円)
✅ 子どもの人数によって支給額が大きく変わるため、申請時に正確に記入することが重要です。
❓Q3. 自動で支給されるの?手続きは必要?
🅰 手続きしないと、1円ももらえません。
遺族年金も障害年金も「自己申請制」です。
必要書類をそろえて、年金事務所や市区町村の窓口で申請する必要があります。
- 死亡診断書や戸籍謄本(遺族年金)
- 初診証明書や診断書(障害年金)
✅ 書類が不足すると審査に時間がかかることも。早めの準備を。
❓Q4. 申請期限はある?遅れてももらえる?
🅰 原則として、申請した月の翌月分から支給開始です。
過去分をさかのぼってもらえるのは原則5年まで(時効)なので、申請が遅れると受け取れない月分が発生する可能性があります。
✅ 亡くなった日、障害認定日が分かったら、早めに相談することが大切です。
❓Q5. パートや主婦でも受け取れる?
🅰 受給の可否は**働き方ではなく、「年金に加入していたか」「保険料を払っていたか」**によって決まります。
- 専業主婦でも、夫の扶養で「第3号被保険者」であれば、条件を満たすことが多いです。
- パート勤務で厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の対象になります。
📝 制度に頼りすぎない備えを|30代が今からできること

「遺族年金」や「障害年金」と聞くと、高齢者向けの制度のように感じるかもしれません。
ですが、今まさに子育てや住宅ローンを抱える30代こそ、万が一に備えておく必要があります。
🔹 制度改正が30代にも影響する理由
2025年の年金制度改正により、遺族厚生年金の支給期間は原則5年の有期給付に変更されました。
これにより、「万が一のときは遺族年金があるから安心」という前提が崩れつつあります。
たとえば生活費が月20万円かかる家庭で、遺族厚生年金が月3万円支給されたとしても、毎月17万円の赤字になります。そして5年後にはその年金も打ち切られる可能性があるのです。
※厚生年金加入歴10年・子ども1人の想定。30代の家庭にとっては現実的な試算です。
💡 公的制度+αの“現実的な備え”を
我が家では、もしもの備えとして以下の2つを実践しています:
✅ 家計のスリム化(節約)
→ 固定費・変動費を見直し、普段から赤字にならない暮らし方を意識
👉 節約の入り口に!生活費を整えるための3ステップ
✅ 投資による資産形成
→ インデックス投資+高配当株で、月数万円の配当収入を構築中
👉 とん家の価値観で選ぶライフスタイル|サイドFIREのための投資戦略と地方移住
こうした対策を進めることで、私はサイドFIRE(セミリタイア型の経済的自立)を目指しています。制度だけに頼らず「自分たちで支える力をつける」ことが、結果的に家族の安心にもつながると感じています。
🔚 遺族年金の改正は「家族を守る行動」のきっかけに
今回の改正は、年金制度を見直すだけでなく、自分の暮らし方を見つめ直すきっかけにもなります。
- 公的制度の仕組みを知ること
- その上で、自分で「選べる力」をつけること
これからの時代、どちらも大切です。
👣 あわせて読みたい関連記事
📘 とん家のプロフィール|3年で2,000万円達成!子育てしながら資産形成
地方移住・FIRE・家族のこと…“わが家のリアル”をすべてまとめました
👉 【プロフィール】とんパパの暮らし方・節約のきっかけと価値観