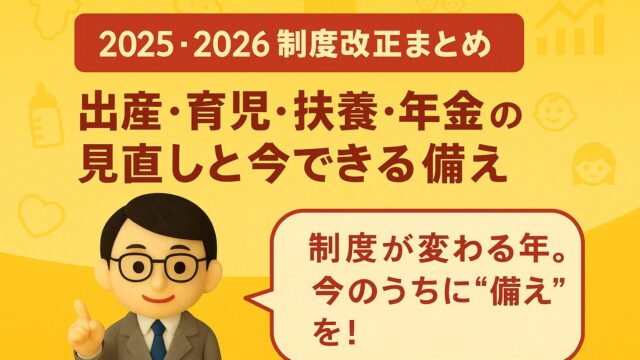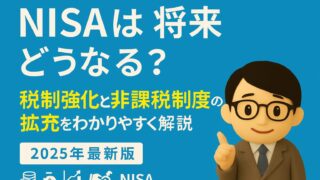一部リンクはアフィリエイトを利用しています。商品・サービスの選定は実体験に基づき、正確な情報提供を心がけています。

保険って、結局入った方がいいの?──保険料、知らず知らずのうちに年間数万円のムダになってない?
そんな疑問に対する明確な答えは、「確率×被害で考える」ことです。
保険は「安心のために入るもの」と思われがちですが、損害が大きく、自分でカバーできないものにだけ備えるのが基本。
本記事では、「何となく加入」から卒業するために、公的保険でどこまで備えられるのか、どんな損害にだけ民間保険で備えるべきなのかを解説します。
とん家が加入していた保険を見直して教育費準備に切り替えたリアルな実例も紹介しつつ、不要な保険を削って家計を改善する方法をお伝えします。将来に“本当に必要な安心”を手に入れるために、まずは保険の考え方から整えてみませんか?
👉この記事でわかること
- 「保険はなんとなく入るもの」という固定観念を見直す考え方
- 保険を判断するシンプルな軸「確率×被害」の活用法
- 我が家が保険を解約し、浮いたお金で教育費を準備した実例
- 公的保険でどこまで備えられるか、私的保険とのバランスのとり方
- 本当に必要な保険の種類(火災・賠償・医療など)の見極め方
📎 関連記事もあわせてどうぞ
- 出産・育児・医療・税制で使える公的制度まとめ
高額療養費・出産一時金など公的制度の使い方を解説 - 教育費はいくらかかる?都内vs地方・公立vs私立を大学まで徹底比較
保険料を削って備えた教育費のリアルなシミュレーション
保険は「入る・入らない」ではなく「確率×被害」で考える

保険は“入るもの”という固定観念
「なんとなく入っておけば安心」「みんな入ってるし心配だから」──
そんなふうに“感覚”で保険に加入している人は少なくありません。
でも本来、保険は「発生確率は低いが、起きたときの損害が大きいリスク」に備えるための手段です。
- 低確率・損失小 → 貯金で備える
- 高確率・損失小 → 貯金で備える
- 低確率・大損失 → 保険で備える
- 高確率・大損失 → 近寄らない
加入するかどうかを判断するには、「そのリスクは起こりやすいか?」「起こったとき、自分は耐えられるか?」という視点──
つまり「確率×被害」の観点が欠かせません。
「損するか得するか」ではなく「困るかどうか」で考える
保険を「元が取れるかどうか」で判断していませんか?
それは“積立”や“投資”の考え方であって、保険の本質とはズレています。
大切なのは、「そのリスクが現実になったとき、自分や家族は“困る”かどうか」。
たとえば…
- 入院費が数十万円かかったとき、貯金で対応できる?
- 火災で家を失ったとき、自分で再建できる?
- 万が一自分が亡くなったとき、家族は生活を続けられる?
こうした問いに対し、“困る可能性が高い”なら保険が必要、“自分で対応できる”なら保険は不要──
このようにシンプルに考えることができます。
世界と日本の保険事情
実は、海外では「必要なければ保険に入らない」のが一般的です。
- アメリカでは、医療費が高額なため医療保険は一般的ですが、生命保険は家族に責任がある人だけが入る傾向にあります。
- ドイツや北欧では、公的保障が充実しているため、個人で加入する民間保険は補完的なものにとどまります。
- フランスでも、必要に応じてミュチュエル(共済型保険)に加入する程度で、全体として“最低限の備え”が前提です。
一方、日本ではどうでしょうか?
日本の社会保障は、実は欧米と比べても遜色なく整備されています。
にもかかわらず──
日本人は必要以上に保険に加入しがちで、家計を圧迫しているのが現実です。
その背景として*日本独自の“保険観のガラパゴス化”が指摘されています(参考:東洋経済)。
- 一億総中流意識:中間層が多く、「保険に入って当然」という空気
- 横並び意識:「みんな入ってるから自分も」という風潮
- 情報の偏り:販売者側に偏った情報ばかりで、そもそも“必要かどうか”を考える機会が少ない
こうした環境では、「どの保険に入るべきか」ではなく、
「自分に本当に必要な保険は何か」から考えることが大切です。
そのためにこそ、まずは「確率×被害」の視点を持つことから始めてみてください。
とん家が保険を見直したリアルな理由
親が大学時代に契約していたがん保険と共済
私が保険に加入したきっかけは、親の強制的加入でした。先ほどの入るのが当たり前が受け継がれてきました。
大学生の頃、親が「とりあえず入っておこう」と私名義でがん保険と共済保険を契約。
当時は保険の意味もよくわからず、
「親がやってくれてるなら…」「安心なんだろうな」くらいの感覚で、思考停止のままスタートしました。
社会人になっても言われるがまま支払っていた
社会人になると、「これからは自分で保険料を払ってね」とまさかの引き継がれました。その金額は、年間で約4万円(月にして3,300円ほど)。
当時の私は、保険を見直すという発想すらなく、「社会人なんだから保険くらい自分で払うのが当たり前」と保険に入らないという選択肢が浮かんでいませんでした。
資産が1,000万円を超えた時点で「保険より資産形成」で良いと判断
そんな私がお金の勉強をし始めて保険の見直しを考えたのは、30代になって資産が1,000万円を超えた頃です。
ふと気づきました。
「仮に入院して高額療養費後の費用だったら、貯金で払えるんじゃないか?」
「月3,300円の保険料を、投資に回した方が将来役立つのでは?」
そこで私は、長年続けていたがん保険と共済を解約。お金の勉強することで「保険で安心を買う」よりも、「貯金や投資で備える」という考え方になり、合理的で納得感がある選択ができました。
保険をやめて浮いたお金で、大学費用が準備できる?

【とん家の例】月3,300円・年4万円の保険料が18年間で約100万円に
実際に我が家では、保険をやめたことで年間4万円(月3,300円)の支出がなくなりました。
このお金を、娘の教育資金として毎月インデックス投資に回すことにしました。
たとえば、18年間を年利4%で運用した場合──
📈 約103万円
※利回り5%なら約114万円、7%なら約139万円にもなります
これは、大学の入学金+初年度授業料に相当する金額です。
まさに、「保険料を見直したことが将来の学費になる」実感を得られた瞬間でした。
仮に7万円や10万円節約できたら?
保険を複数契約している家庭では、年間7〜10万円以上払っているケースもあります。
この金額をそっくり投資に回したと仮定すると──
- 年間7万円(約月5,800円)→ 約180万〜250万円
- 年間10万円(約月8,300円)→ 約260万〜360万円
年間10万円になると、大学4年間の学費をカバーできるレベルです。
大学費用と比較すると…
とん家の教育費まとめ記事(教育費シミュレーションはこちら)でも紹介しているように、国公立大学の学費であれば約300万円程と想定されます。
| 大学区分 | 学費(円) |
|---|---|
| 国公立大学(文系) | 約282万 |
| 国公立大学(理系) | 約300万 |
| 国公立大学(医歯系・6年) | 約350万 |
| 私立大学(文系) | 約452万 |
| 私立大学(理系) | 約585万 |
| 私立大学(医歯系・6年) | 約3,000万 |
今回の例でいえば、月3,300円でも大学費用の約1/3を準備できる計算です。このように、保険をやめたことで“安心を捨てた”わけではなく、リスクに備える手段を「保険から資産形成」に切り替えたことになります。
🔍 保険をやめたことで、未来の選択肢が増える
無駄に思える出費でも、見直すことで将来に“活きるお金”に変えられる
公的保険でどこまで備えられるのか?

保険を見直すとき、最初に確認すべきなのは──
「公的保険(社会保障制度)でどこまでカバーできるのか?」です。
私たちはすでに、病気・出産・失業・死亡といったリスクに対して、一定の保障を受けられる仕組みの中に生きています。
高額療養費制度や出産育児一時金
医療費が高額になっても、自己負担額が一定水準で抑えられる「高額療養費制度」があります。
たとえば、月100万円の医療費がかかったとしても、年収や年齢に応じて自己負担額は8万円前後まで軽減されます。
また、出産時には出産育児一時金(原則50万円)が支給され、多くのケースで自己負担を大幅に減らすことができます。
遺族年金・障害年金・失業手当
万一のときにも、公的保障はあります。
- 遺族年金:子どもや配偶者が一定の生活費を受け取れる
- 障害年金:重度の障害が残った場合に年金形式で受給
- 失業手当(雇用保険):退職後も一定期間の生活を支援
こうした保障があることを知らずに過剰な死亡保険や収入保障保険に加入している人も少なくありません。
過不足はあるが「ベース保障」として機能している
もちろん、すべてのケースを100%カバーできるわけではありません。
しかし、これらの制度を「ベースの保障」として捉え、その上で必要な部分を私的保険で補うという順序が基本です。
🔍 まずは制度を知る → 不足するリスクを把握する → それでも足りない場合に保険で補う
この流れを押さえておけば、「なんとなく加入」や「勧められたから入る」といった曖昧な保険選びを避けられます。
📎 関連リンク:
[知らないと損する!出産・育児・医療・税制で使える公的制度まとめ]
[遺族年金・障害年金のまとめ]
それでも入るべき保険とは?“備えるべき損害”の見極め方

「公的保障で足りるなら、もう保険は不要ですか?」
という問いはYESですが、実際には自分でカバーするのが困難なケースがあります。その際には、民間保険が力を発揮します。
火災・地震・個人賠償責任保険など「自分でカバーできない損害」
保険で優先的に備えるべきなのは、“自分の資産では到底カバーできないような大きな損害”です。
特に、以下の3つの分野は生活に与える影響が大きく、多くの家庭にとって“必要性が高い保険”といえます。
🔥 火災保険(賃貸でも必須)
「火災保険=持ち家の人が入るもの」と思っていませんか?
実は、賃貸住宅でも火災保険はほぼ必須です。
賃貸契約時には、以下のようなリスクに備えるため、火災保険への加入が義務付けられていることが一般的です。
- 自分の部屋からの出火で、建物や他室に被害を与えた場合
- 洗濯機やエアコンの水漏れで階下に損害を与えた場合
- 火災や落雷などで自分の家財が損傷した場合(例:PC、家電、家具)
年間5,000〜20,000円程度で加入できることが多く、必要最低限の補償としては合理的な選択肢です。賃貸の際には不動産会社から提案されますが、個人で加入すると費用負担を削減できます。詳細は以下の記事をご覧ください。
【引越し・初期費用を10万円下げる方法】4回の引越しから学んだリアルな節約術
🌍 個人賠償責任保険
「他人にケガや損害を与えてしまった」ときに備えるのが個人賠償責任保険です。たとえば…
- 子どもが自転車で歩行者にケガをさせた
- ボール遊びで他人の車や窓ガラスを破損した
- 飼い犬が他人に噛みついてケガを負わせた
このような「まさか」による損害が億単位に及ぶケースもあり、保険料による備えが必要です。
最近では、自動車(自転車)保険や火災保険に年間1,000〜2,000円程度で付けられる特約としてセットされることも多く、費用負担も少なく済みます。
🌏 地震保険(持ち家・賃貸ともに検討の価値あり)
地震による建物損壊や家財の損失に備えるのが地震保険です。特に日本は地震大国であり、火災保険では地震被害は補償されません。
- 持ち家の場合:住宅ローンがある家庭では加入が強く推奨されます
- 賃貸でも:自分の家財(アンティーク家具など値段が付く1点もの)を守る目的で検討の価値あり
ただし、補償内容や保険料に地域差が大きいため、「保険料に見合った備えになるか?」を慎重に判断する必要があります。
🔍 まとめ:自分で備えきれない損害にこそ、保険を使う
✔ 火災保険は「賃貸でも必須」
✔ 賠償責任保険は「子育て家庭ほど重要」
✔ 地震保険は「持ち家・地域によって優先順位が変わる」
医療保険・がん保険は“自己資産とのバランス”で判断
一方で、上に紹介した以外の医療保険やがん保険については、公的保険+貯蓄で対応できる家庭も少なくありません。
- 入院費や治療費が高額でも、高額療養費制度で一定額に抑えられる
- 自分や家族が貯蓄で数十万円を出せるなら、保険に頼る必要は薄れる
ただし、貯蓄がまだ少ない若年層や、子育て初期で不安が大きい家庭では、一定期間だけ加入しておくのも選択肢です。
保険のプロが入ってる保険を聞いてみる
もし自分では判断がつかない場合は、「保険のプロが実際に入っている保険」を参考にしてみるのも一つの方法です。
保険の見直し相談サービスやFPのアドバイスを受ける際は、「売るための保険」ではなく“リスクベースで必要性を一緒に考えてくれる人”を選ぶのがポイントです。
あわせて読みたい|保険を考える前に「固定費」全体を整理したい方へ
保険は家計の中では「固定費」の一部です。保障内容だけで判断するのではなく、家計全体の支出バランスを把握したうえで考えることで、無理のない見直しがしやすくなります。
保険を含めた固定費の考え方を整理したい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
固定費・変動費・公的制度をどう組み合わせて家計を整えるかをまとめた記事です。「まず何から見直すべきか」を整理したい方に向いています。
保険を含む固定費を、項目ごとにどう見直していくかを解説しています。
本記事の考え方を、家計全体に広げたい方におすすめです。
実体験ベースで、固定費を整えた結果どう家計が変わったかをまとめています。
「見直すと本当に楽になるの?」という疑問を持つ方に向けた記事です。
最後にここまでの内容を踏まえて、とん家がどんな考え方で保険を選び、どこを削り、どこを残しているかを整理します。
まとめ:保険は「怖いから入る」から「判断して選ぶ」時代へ

保険に対する考え方は、これからの時代、「なんとなく怖いから入る」から「リスクに応じて選ぶ」へ変えていく必要があります。そのときに役立つのが、「確率×被害」というシンプルな考え方です。
感覚ではなく、合理的に選ぶ
- めったに発生しないが、発生したときの損害が大きい
- 突発的に発生して自分でカバーできない損失になる
こうしたリスクには、保険で備える価値があります。逆に、起こる確率が高くても、貯金や社会保障で対応できる範囲なら、保険に頼る必要はありません。大切なのは、“なんとなく不安だから”という感情ではなく、「起きたとき、自分や家族が困るかどうか」で判断する視点です。
「備える=保険」だけではなく「貯蓄や投資」も手段
保険に入らずに済むための選択肢は、実は他にもあります。それが、貯蓄やインデックス投資によって「耐える力」を高めることです。
我が家でも、医療・がん・死亡保険をすべて解約し、浮いた保険料(年間4万円)を娘の教育費として投資に回すことにしました。その結果、18年間で約100万円を準備できる見通しが立っています。
安心を得るために、“制度と情報”を味方につける
公的保険(高額療養費制度や遺族年金など)や社会保障制度を正しく理解すれば、「もしものとき」も実は多くの場面でカバーされていることがわかります。
加えて、自分が抱えるリスクを整理し、それに合った保険を必要最小限だけ選べば、ムダなく・安心できる暮らしが実現できます。
🔍 「保険=安心を買う」ではなく、「確率×被害で判断して選ぶ時代」に入っていると感じています。