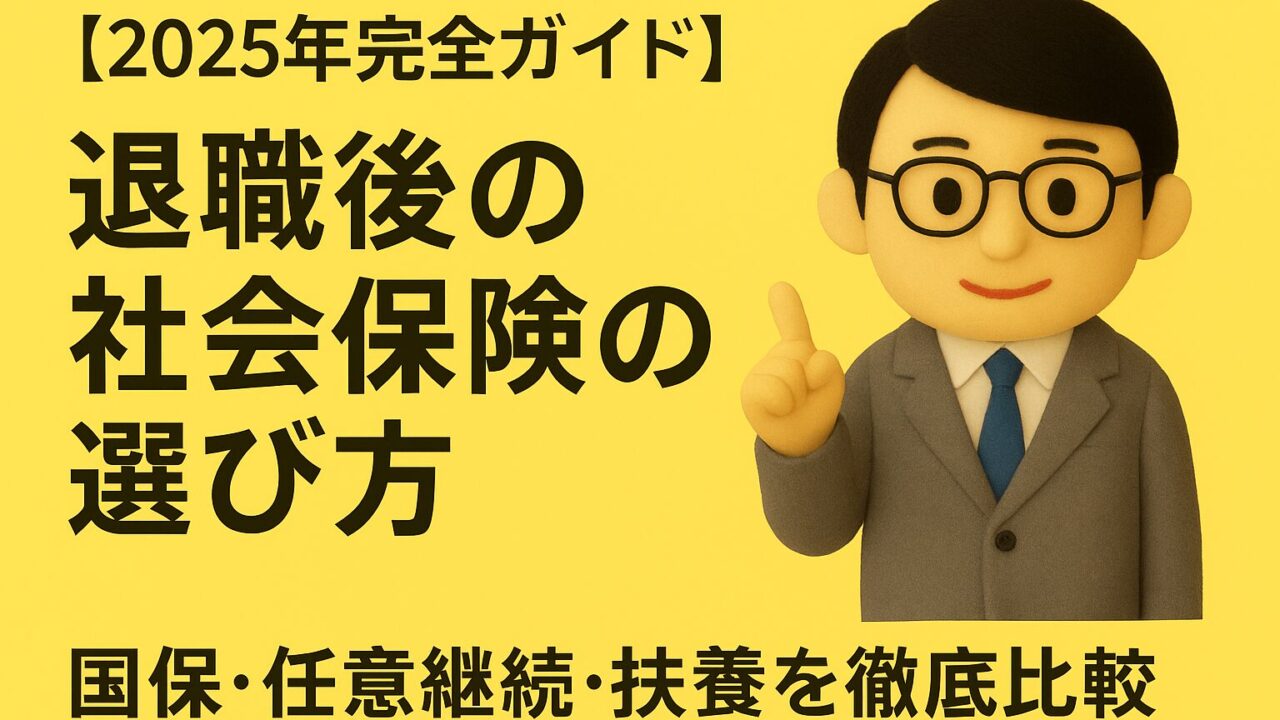一部リンクはアフィリエイトを利用しています。商品・サービスの選定は実体験に基づき、正確な情報提供を心がけています。

「退職後の社会保険、どの制度を選べば一番お得なんだろう?」
転職や退職のタイミングで、多くの人が直面するのがこの疑問です。
社会保険の選び方は、家計に直結する大きな問題です。特に扶養家族がいる場合は、保険料の負担が年間で数十万円単位の差になることもあります。だからこそ、国保・任意継続・扶養といった選択肢を正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、退職後の社会保険の選択肢を整理し、年収0円〜700万円のシミュレーションを用いて比較します。また、個人事業主(青色申告)でも扶養に入れるのか?、控除を活用して130万円以内に収める方法についても詳しく解説します。
退職後の社会保険を正しく選ぶことで、無駄な出費を抑えながら、安心して次のキャリアやライフプランを考えることができます。
👉この記事でわかること
✅ 退職後の社会保険の選択肢(国保・任意継続・扶養)
✅ 各制度のメリット・デメリット
✅ 年収0円〜700万円の保険料シミュレーション
✅ 個人事業主(青色申告)は扶養に入れるのか?
✅ 控除を活用して130万円以内に収める方法
👉あわせて読みたい退職後に重要な関連記事
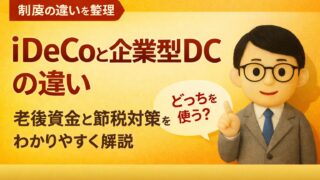

退職後の社会保険の選択肢|国民健康保険・任意継続・扶養の比
退職後に選択できる主な社会保険の加入方法は以下の3つです。こちらの表を参考に私は妻の扶養に入り、個人事業主として今後の副業収入を作るために昼の時間を作ることにしました。
扶養に入ると失業保険をもらえませんが、実際には社会保険料でもらえる金額と±0になる可能性が高いと考えています(詳細は「家族の被扶養者になる」で記載)。
1. 任意継続被保険者制度を利用する
- 退職前に2ヶ月以上健康保険に加入していた場合、退職後20日以内に手続きを行うことで、最長2年間、在職時の健康保険を継続できます。
- 会社負担がなくなるため、在職時よりも保険料が増加する可能性があります。、協会けんぽ(東京都・任意継続)の場合だと以下のようになります。
| 年収(万円) | 標準報酬月額(円) | 年間保険料(円) |
|---|---|---|
| 0 | 58,000 | 68,736 |
| 100 | 88,000 | 104,064 |
| 200 | 98,000 | 115,776 |
| 300 | 148,000 | 174,336 |
| 400 | 190,000 | 223,776 |
| 500 | 240,000 | 282,336 |
| 600 | 290,000 | 340,896 |
| 700 | 340,000 | 399,456 |
※40歳未満の単身者の場合。介護保険料は含まない。
2. 国民健康保険(国保)に加入する
- 市区町村が運営する健康保険に加入します。前年の所得を基に計算されるため、所得が高いと保険料も高くなります。国民健康保険(東京都・新宿区の場合)の場合は以下の表のようになります。
- 国保は扶養の概念がないので扶養者がいる場合は選択肢にならないと思います。私の場合は妻がまだ働いているので一応選択肢としては検討しました。
| 年収(万円) | 年間保険料(円) |
|---|---|
| 0 | 195,000 |
| 100 | 195,000 |
| 200 | 195,000 |
| 300 | 306,563 |
| 400 | 417,563 |
| 500 | 528,563 |
| 600 | 639,563 |
| 700 | 750,563 |
※40歳未満の単身者の場合。扶養家族がいる場合は加算されます。
※40歳以上は介護保険料が別途加算。
3. 家族の被扶養者になる
配偶者や親が会社の健康保険に加入している場合、扶養に入ることで保険料の負担なしで加入できます。このケースの場合、配偶者控除を30歳以下であれば扶養控除を使用できる可能性もあります。私の場合は半年分の給与があるため、配偶者控除等は難しいですが、保険料という意味ではやはり圧倒的に有利です。
デメリットとして失業保険をもらえないことです。私の場合は自己都合の退職となり3ヶ月ほどで60万円程度の支給となります。自己都合退社の場合、失業保険を実際に受け取るまでに社会保険を支払う必要があり、任意継続の場合の1番収入のない保険料である68,736円でも8ヶ月ほどで60万円近くなり、失業保険±0になる可能性が高いと考えています(仕事を辞めた次の月は確実に68,736円以上になります)。
- 収入要件(年収130万円未満など)を満たす必要があります。
- 配偶者・子供・親など扶養関係があることが必要
- デメリットは失業保険がもらえない
- 扶養者の加入する健康保険によって条件が異なるため要確認
個人事業主(青色申告)も扶養に入れる?

個人事業主でも一定の条件を満たせば扶養に入れる
結論としては個人事業主でも一定の条件を満たせば扶養に入ることが可能です。
一定の条件とは、事業収入から必要経費を差し引いた**「課税所得」が130万円未満であることです。
私は日中の家事をする以外の時間を今後の収入を作るために充てたいため、娘を保育園にお願いすることにしています。ここは現在の保育園がとても気に入っているのでこのまま通わせたいという気持ちとセットでこの判断をしています。
個人事業主が利用できる3つの利点
現在副業収入がないので1年目からたくさんの金額が稼げるとは思っていません。ただ、子供を保育園にお願いできる他に以下の3つの利点があると思っています。
- 家賃などが必要経費となる、課税所得から除外できる(130万円未満の可能性が高くなす)
- 控除を利用して、翌年の税金を抑えることができる
- 赤字を3年繰り越しできる
この3点を有効活用して、収入の減少が家計を圧迫しないように努力します。
個人事業主が利用できる5つの控除
こちらの章では個人事業主が利用できる控除を紹介させていただきます。全部が全員できるわけではないので、自分で判断するか、税理士に相談する必要があります。
私が使用するのは1と2と思っています。3は企業した際や稼げるようになってから考えることだと思っています。
1. 必要経費の計上
- 事業にかかった費用(家賃、通信費、交通費、消耗品費など)を計上し、所得を抑える。
2. 青色申告特別控除
- 最大55万円(e-Tax申告なら65万円)の控除を受けられる。
3. 小規模企業共済掛金控除
- 掛金が全額控除されるため、所得調整に有効。
4. 国民年金・健康保険料控除
- 支払った国民年金や健康保険料を所得控除に適用。
5. 生命保険料控除
加入している生命保険・介護医療保険の控除を活用。
まとめ どの健康保険を選ぶべきか?【総合比較】
✔ 任意継続 → 扶養家族がいる&在職中の保険をそのまま継続したい場合におすすめ。ただし、2年まで。
✔ 国民健康保険 → 所得が低い場合に有利。扶養家族も対象になるが、収入が高いと負担が大きい。
✔ 家族の扶養 → 収入が130万円未満なら最もお得。 控除を活用すれば個人事業主でも加入可能!
私の場合は「扶養に入る&個人事業主」になりましたが、退職後の社会保険を選ぶ際には、自身の収入状況・家族構成・扶養条件をよく確認し、最適な選択をしましょう!
| 健康保険の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 任意継続 (協会けんぽ) | 退職前の健康保険を継続できる。扶養家族も継続可能 | 会社負担がなくなり、保険料が増加。 最大2年間のみ |
| 国民健康保険(国保) | 所得が低ければ保険料も安くなる | 所得が高いと保険料も上がる。扶養家族も保険料の対象になる |
| 扶養に入る | 保険料が無料。家族の健康保険を利用できる | 収入要件を満たさないと加入できない |
第一弾の退職時に発生する税金の注意点、住民税や所得税の支払い方法や第二弾のの確定拠出年金(DC)やiDeCoの移管手続き、退職後の運用方法について解説しているので興味があればこちらから覗いてみてください。
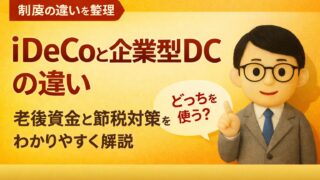

▶️ 関連記事もあわせてチェック!
📘 とん家のプロフィール|3年で2,000万円達成!子育てしながら資産形成
地方移住・FIRE・家族のこと…“わが家のリアル”をすべてまとめました

🔸 【FIREの考え方と実践】暮らしとお金のバランスを考えたい方へ

🔸 【節約×投資】収入が増えなくても資産が増える家計づくり