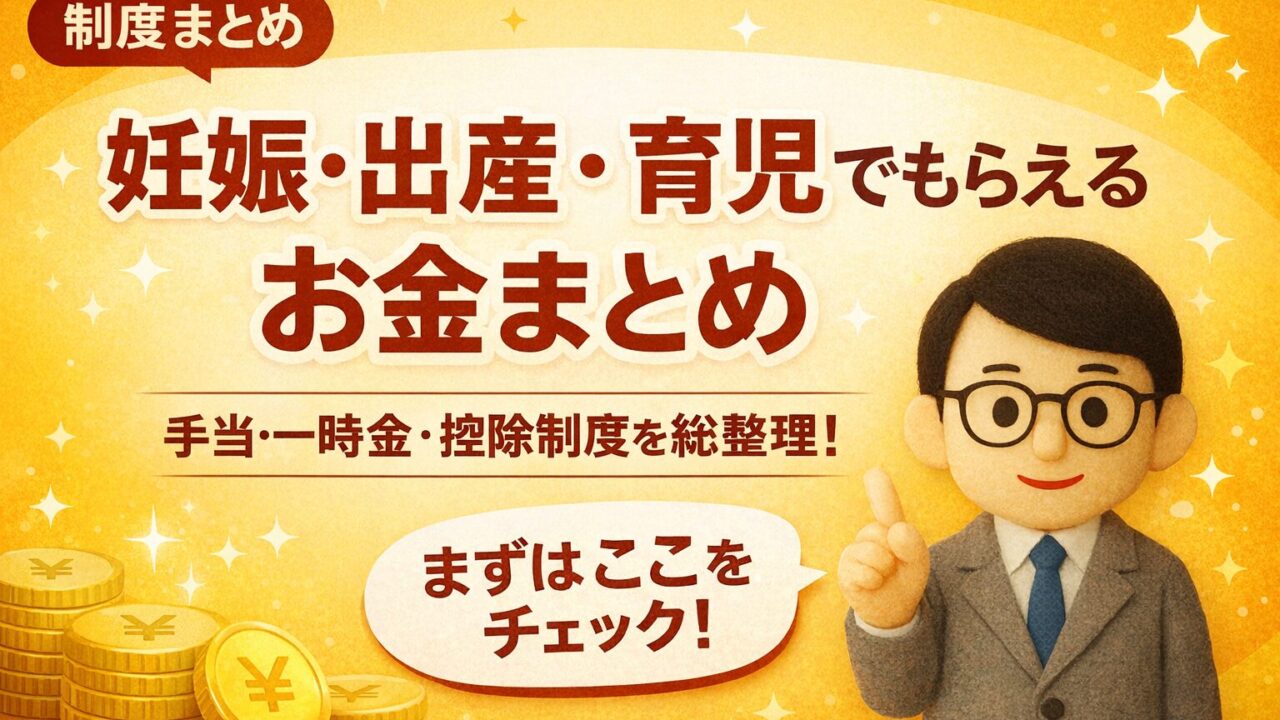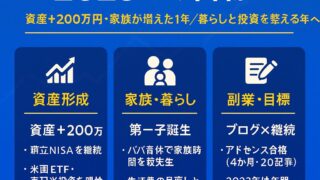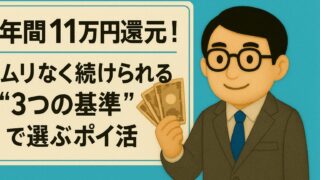一部リンクはアフィリエイトを利用しています。商品・サービスの選定は実体験に基づき、正確な情報提供を心がけています。

はじめに
妊娠・出産には、健診・入院・出産費用と何かと出費がかさみます。でも実は、申請すればもらえる「補助金」「手当」「還付金」がたくさんあるのをご存じでしょうか?
本記事では、2025年最新の制度改正を反映しながら、
- 自治体(市区町村)
- 職場(雇用主)
- 健康保険組合
- 税務署(確定申告)
など、申請先ごとに妊娠・出産でもらえるお金をわかりやすく解説します。見やすいチェックリスト付きで、もれなく申請できるようサポートしますので、ぜひブックマークして活用してください!
妊娠・出産でもらえるお金は意外と多い!
平均的な出産費用(正常分娩)は約45〜55万円。
これに加えて妊婦健診代、入院中の差額ベッド代や交通費なども含めると、出産1回あたり60万円以上かかるケースもあります。
しかし、以下のようなお金は「申請すれば支給される」もの。
知らなければもらえず損することも多いため、出産準備とあわせて情報収集しておきましょう。
【自治体から】妊娠中・出産後にもらえる制度

妊婦健診の補助券(母子手帳と同時にもらえる)
妊婦健診は基本的に保険適用外で、1回あたり5,000円〜10,000円ほどかかります。妊娠中に14回程度受診が必要とされており、合計すると10万円以上の負担になることも珍しくありません。
これを軽減するため、自治体は妊婦健康診査費用補助券(補助チケット)を交付しています。
- 市区町村役所で母子手帳を受け取るときに一緒にもらえます。
- 補助の回数や金額は自治体によって異なりますが、14〜20回分が一般的です。
- 全額補助されるわけではなく、一部自己負担が残るケースもあります。
産院によっては補助券が使えないこともあるため、里帰り出産を検討している方は早めに確認が必要です。
私は里帰り先では2週間健診があったのですが、住んでいる地域では2週間検診がなく補助券はなく、5,000円程かかりました。地域によって、補助券の内容や健診のタイミングは異なるようです。
児童手当(2024年10月制度改正)
児童手当は、子育て家庭に対して国が支給する給付金制度で、2024年10月から制度が大幅に見直されました。
- 所得制限が撤廃されたことで、共働き高所得世帯も対象に。
- 支給対象年齢が「中学卒業まで」から「高校卒業まで(18歳の3月末)」へと延長。
- 第3子以降は月額3万円に増額され、より手厚いサポートとなっています。
| 子どもの人数 | 支給額(月額) |
|---|---|
| 第1・2子 | 15,000円(0〜3歳未満)、 10,000円(3歳〜高校生) |
| 第3子以降 | 一律30,000円(3歳〜高校生) |
支給は偶数月に2ヶ月分まとめて振り込まれます。
出生届と同時に申請できるため、出産直後のバタバタ時期を避けるためにも、事前に必要書類を確認しておくのがおすすめです。
小児医療費助成制度
子どもが病気やケガで病院にかかったとき、医療費がほぼ無料または定額で済む制度が「小児医療費助成制度」です。
- 多くの自治体で中学卒業(15歳)まで、または高校卒業(18歳)まで適用。
- 自己負担0円のところもあれば、500円〜1,000円程度を定額で支払う形式の地域もあります。
- 通院・入院ともに助成されるのが一般的です。
申請により「医療証(マル子など)」が交付され、医療機関の窓口で提示することで助成を受けられます。
引越し後の手続き忘れなどで「知らずに全額支払ってしまった」という声もあるため、妊娠中から事前に確認しておくと安心です。私は引越しのタイミングで少し空いたタイミングでの
【職場から】働くパパママがもらえるお金

出産手当金(会社員ママ向け)
出産手当金は、会社員・公務員など社会保険に加入している女性が、出産のために仕事を休んでいる間にもらえるお金です。
- 支給対象期間は「出産予定日以前の42日間」と「出産後の56日間」の合計98日間(双子以上の場合は出産前98日間)。
- 支給額は、1日あたり「標準報酬日額 × 2/3」で計算されます。
- 産休中に給与が支払われないことが条件となります。
申請は勤務先を通じて行い、健康保険組合や協会けんぽから直接支給されます。
産休開始後、給与がなくなる期間を補填する重要な制度なので、必ず確認しましょう。
育児休業給付金(パパ育休にも対応)
育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が育児のために仕事を休んだ場合に支給される給付金です。
パパ・ママどちらも対象で、「パパ育休」の場合も同様に支給されます。
- 育休開始から180日間は、休業開始前の賃金の67%が支給されます。
- 181日目以降は50%に減額されますが、社会保険料が免除されるため**実質的な手取りは約80%**となることが多いです。
- 支給期間は原則1歳まで、延長で最長2歳まで取得可能です。
特に男性の育休取得者向けには、**出生後8週間以内に連続or分割して休業を取ることで支給される「出生後休業支援給付金」**も別制度として用意されています。
育児時短就業給付金の概要【2025年4月スタート】
育休後、いきなりフルタイムに戻るのが難しい…。そんな時に役立つのが、「育児時短就業給付金」という新制度です。
2025年4月から始まり、2歳未満の子どもを育てながら時短勤務を選んだ方に、給与の一部(最大10%)が支給されます。
制度概要(いつから・誰が対象?)
- 開始時期: 2025年4月1日
- 対象者: 雇用保険の被保険者で、2歳未満の子を養育するために週所定労働時間を短縮して働く方
- 育児休業給付からの継続、または就業前2年のうち賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月あること
- 支給対象月ごとに「被保険者かつ時短就業していること」
- 他の育児休業や介護給付と重複していないこと
支給額の計算方法(ざっくり言うと「時短後の給料×10%」)
基本の計算式
- 賃金が開始時賃金月額の90%以下の場合
→ 支給額 = 賃金額 × 10% - 賃金が90%超〜100%未満の場合
→ 支給額 = 賃金額 × 調整支給率
※調整支給率 = 9,000 ÷ 賃金率(%) − 90 - 賃金+支給額が支給限度額を超える場合
→ 支給額 = 支給限度額 − 賃金額
具体例(時短で月給30万 → 22.5万になった場合)
- 開始時賃金月額:30万円
- 時短後賃金:22.5万円(=30万円の75%)
- 90%以下なので、支給額は 22.5万円 × 10% = 22,500円
支給限度額・下限額(2025年7月まで)
- 支給限度額:459,000円
- 最低支給額:2,295円(これ未満は対象外)
- 開始時賃金月額の上限:470,700円
- 開始時賃金月額の下限:86,070円
支給期間と終了の条件
支給対象期間
→ 原則として時短就業を開始した月から終了した月まで
支給が終わる条件(以下のいずれか早い月で終了)
- 子が2歳になる前月まで
- 産休・育休・介護休業を再度取得した前月
- 別の子の時短就業を始めた月の前月
- 子が死亡、または同居・養育しなくなった場合
フレックスタイムや変形労働制でも使える?
- 就業規則で定められた**「週所定労働時間」**を短縮していれば対象となります。
- 勤務形態が柔軟でも、「時短勤務」としての形式が整っていれば申請可能です。
申請方法とスケジュール
申請は誰がする?
- 原則:事業主が申請(ハローワークへ)
- ※本人希望で、本人申請も可能
申請スケジュール
- 初回:時短勤務開始月の初日から4か月以内
例:7月に開始したら11月末までに申請 - 2回目以降も、対象月の初日から4か月以内
→「次回支給申請日指定通知書」に従って申請
申請方法
- ハローワークへの提出(郵送・持参)
- 電子申請(e-Gov)も可能
- 特定法人(資本金1億円超など)は電子申請が義務
必要書類(一部)
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 出生証明書類(住民票など)
- その他、詳細は厚労省のパンフレット参照(P10-11)
✅ 最後に|制度は新しいけれど「使える人」はチェックを
この制度はまだ始まったばかりですが、「育休明けに時短勤務する人」なら対象となる可能性が高いです。
パパママどちらでもOKなので、復職後の家計サポート策として知っておいて損はありません。
【健康保険から】加入者が受けられる給付金

出産育児一時金(50万円)
健康保険に加入している人(または扶養されている配偶者)が出産した場合、「出産育児一時金」が1人あたり50万円支給されます。
- 医療機関に直接支払われる「直接支払制度」がほとんどで、窓口での支払い負担を減らせます。
- 自費の出産費用が50万円を超えなければ、追加の支払いは不要です。
- 双子の場合は100万円、三つ子なら150万円と、人数分支給されます。
申請は原則不要で、病院での手続きだけで済むケースが多いですが、加入している健康保険によっては申請が必要な場合もあるため要確認です。
高額療養費制度(帝王切開・異常分娩など)
通常の自然分娩は保険適用外ですが、帝王切開や妊娠高血圧症候群など、医療行為を伴う出産は保険適用となり、費用が高額になることもあります。
このとき、高額療養費制度を使えば、1ヶ月あたりの医療費負担が一定額(約8万円程度)を超えると、その分が後から払い戻されます。
- 所得区分によって上限額が異なる(例:一般所得者→約8万円)
- 差額ベッド代・食事代・自費分は対象外
- 事前に「限度額適用認定証」を取得すると、その場で支払いを抑えられる
健康保険組合や共済組合は申請しなくても2,3ヶ月後に差額を支給してくれますが、それ以外の健保保険などは申請が必要なので職場に相談してみてください。
医師から帝王切開が必要と診断された場合は、事前に健康保険組合に申請し「認定証」を取得しておくのがベストです。私は認定証が間に合っておらず、手続きが大変でした。
最後に年収毎の上限額を紹介します。
| 適用区分 | 1ヶ月の上限額(世帯) |
| 住民税非課税者 | 35,400円 |
| 年収約370万円以下 標準報酬月額 26万円以下 | 57,600円 |
| 年収約370万円から約770万円 標準報酬月額 28万円以上53万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| 年収約770円から約1,160万円 標準報酬月額 53万円以上83万円以下 | 167,400円+(医療費-553,000)×1% |
| 年収約1,160万円以上 標準報酬月額 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
【税務署から】確定申告で戻るお金

医療費控除(年間10万円超で対象)
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告によって所得税の一部が還付される制度です。
妊娠・出産関連でも、以下のような費用が控除対象になります:
- 妊婦健診費用(自費分)
- 分娩・入院費用
- 通院にかかった公共交通機関の運賃
- 不妊治療費や助産師によるケア費用
対象にならない費用の例は以下になります:
- 出産入院時の日用品代
- 無痛分娩のための講義受講料
- 妊娠検査薬代
- 自家用車通院した際のガソリン代
- 赤ちゃんのオムツ代
医療費控除は「出産費用の一部でも戻るチャンスがある」制度です。領収書・交通費メモはまとめて保管しておき、翌年の確定申告時に活用しましょう。
妊娠・出産でもらえるお金【まとめチェックリスト】
| 種類 | 支給元 | 支給額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 妊婦健診助成 | 自治体 | 約10〜15万円相当 | 母子手帳交付時に受け取る |
| 児童手当 | 自治体 | 子ども1人あたり 月1万〜3万円 | 所得制限なし・高校卒業まで対象 |
| 小児医療助成 | 自治体 | 実質無料も多い | 所得や年齢により対象が異なる |
| 出産手当金 | 職場経由 | 給与の2/3 | 社会保険加入が条件 |
| 育児休業給付金 | ハローワーク | 実質手取り80%前後 | 最長2年まで可能 |
| 出産育児一時金 | 50万円/人 | 医療機関に直接支払も可 | 申請不要の場合も多い |
| 高額療養費制度 | 健康保険 | 所得により上限あり | 帝王切開・入院費用など |
| 医療費控除 | 還付額は 人による | 年間10万円超で対象 | 確定申告が必要 |
【2026年版】今後予定・検討されている制度の動き
ここまで現行の支援制度を整理してきました。2026年に向けて大きな制度改正は予定されていませんが、新たに始まる制度や、今後検討が進められている動きがあります。
最後に、2026年版として押さえておきたいポイントを簡単に見ていきましょう。
子ども・子育て支援金制度(2026年開始予定)
2026年度から、新たに「子ども・子育て支援金制度」が始まる予定です。健康保険料とあわせて徴収され、児童手当などの子育て支援策の財源に充てられます。
この制度は「もらえるお金」そのものではありませんが、妊娠・出産・子育て支援を支える新しい仕組みとして、2026年版では押さえておきたい動きです。
※制度の詳細(負担額など)は今後正式に示される予定です。
出産費用の公的医療保険適用に関する議論(検討段階)
現在、出産費用を公的医療保険の対象とする(いわゆる「出産の保険適用」)議論が進められています。
実現すれば、自己負担の考え方や出産育児一時金の位置づけが変わる可能性がありますが、2026年時点では制度化は未確定であり、今後の検討課題とされています。本記事では、確定した制度改正があった場合に随時反映していく予定です。
👉合わせて読みたい関連記事
- 【体験談】パパ育休4.5ヶ月のリアルと制度活用まとめ
- 【2025年最新版】男性の育休制度と給付金の全解説|実質100%支給の新制度にも対応!
- 【2025年版】医療費控除・高額療養費制度とは?|申請方法や戻る金額をわかりやすく解説
- 知らないと損する!出産・育児・医療・税制で使える公的制度まとめ
まとめ|制度を知って、安心して子育てスタートを

妊娠・出産はお金がかかる一大イベントですが、制度をしっかり活用すれば家計負担を大きく減らすことができます。
妊娠・出産は、人生のなかでもっとも出費が集中するタイミングの一つです。
でも、この記事で紹介したように、国・自治体・職場・保険から「もらえるお金」や「戻ってくるお金」が数十万円単位で用意されています。
🔍 こんな人こそ、制度をフル活用すべき!
- 出産にかかる費用をできるだけ抑えたい
- 共働きで制度の確認・申請が後回しになりがち
- 初めての妊娠・出産で何から準備すればいいか不安
- パパ育休や時短勤務なども検討中
🎯 次のアクションとしておすすめ!
- 📌 この記事をブックマーク・保存して、出産準備のスケジュールに組み込む
- ✅ 自分が該当する制度にチェックを入れて、漏れなく申請
- 🔗 あわせて読みたい関連記事で、出産後の家計や育児支援も先回りで学ぶ
出産・育児は家族のスタートライン。
お金の制度を味方につけて、安心して家族の時間を楽しめる環境づくりをしていきましょう!
👣おすすめ記事
📘 とん家のプロフィール|3年で2,000万円達成!子育てしながら資産形成
地方移住・FIRE・家族のこと…“わが家のリアル”をすべてまとめました
👉 【プロフィール】とんパパの暮らし方・節約のきっかけと価値観
💡 【節約まとめ】子育て3人家族が固定費・変動費を徹底見直し!
生活水準を下げずに支出を削減したノウハウを紹介しています
👉 節約の入り口に!生活費を整えるための3ステップ
🔥 【サイドFIRE戦略まとめ】投資と暮らしのちょうどいい距離感
高配当+インデックス投資の戦略と、地方での暮らしの実践例
👉 とん家の価値観で選ぶライフスタイル|サイドFIREのための投資戦略と地方移住