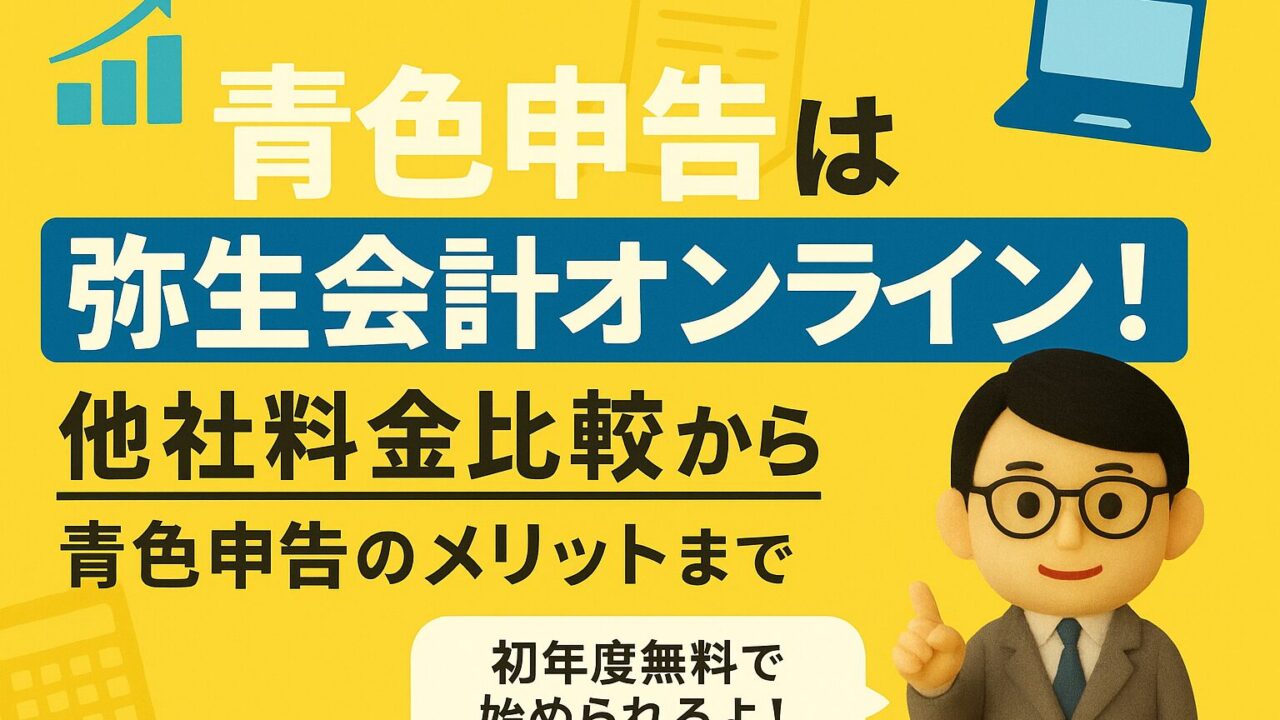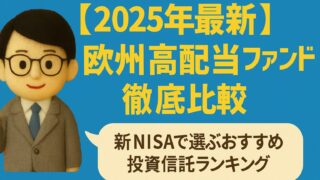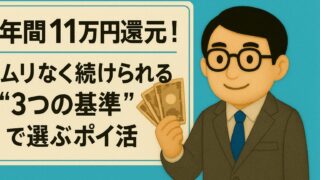一部リンクはアフィリエイトを利用しています。商品・サービスの選定は実体験に基づき、正確な情報提供を心がけています。
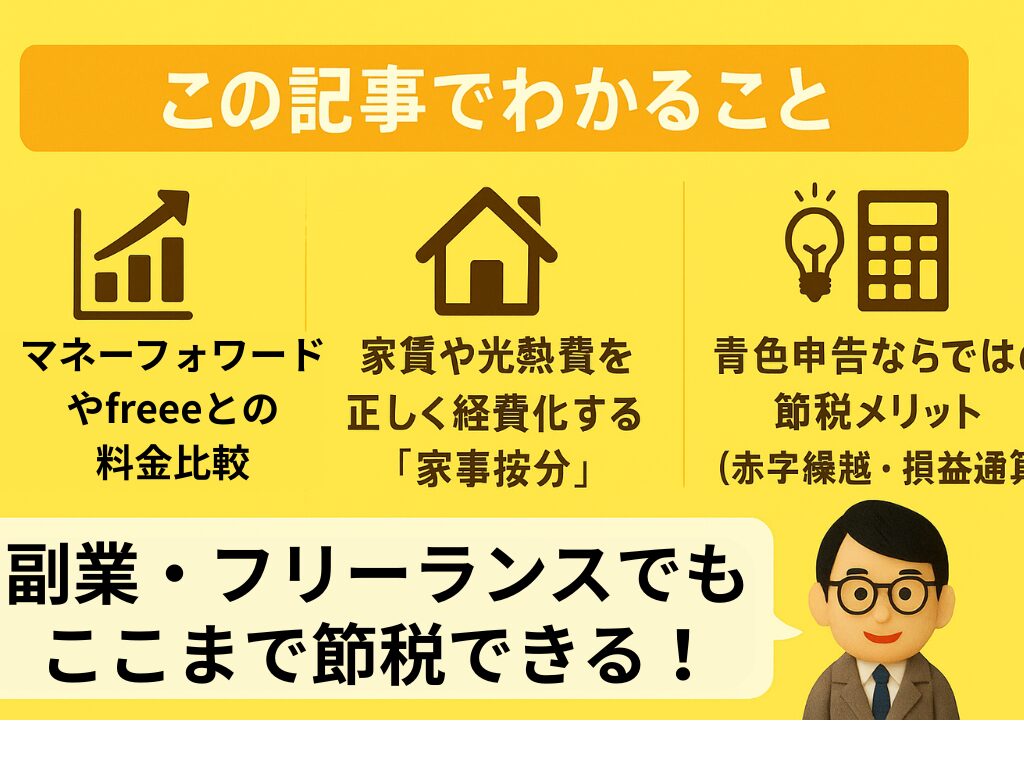
青色申告を始めたいけれど、「会計ソフトは弥生・マネーフォワード・freeeのどれが良い?」「簿記の知識がなくても65万円控除は受けられるの?」と迷う方は多いと思います。
私自身も簿記はこれから勉強する段階で、現在は主夫+副業という形でサイドFIREを目指し、仕事復帰までの半年間でストック収入を育てたいと考えています。2026年には地方移住と再就職を予定しており、今のうちに青色申告の基盤を整えることが欠かせないと感じました。
この記事でわかること
この記事では、私が実際に弥生会計オンラインを使って青色申告を準備した体験談をもとに、
- 他社(マネーフォワード・freee)との料金比較
- 家賃や光熱費を正しく経費化する「家事按分」の方法
- 青色申告ならではの節税メリット(赤字繰越・損益通算)
- e-Taxを利用して65万円控除を狙う方法
までをわかりやすく解説します。「青色申告ソフト選びに迷っている」「弥生会計オンラインの評判や実際の使い方を知りたい」という方に役立つ内容になっています。
👉まず基本的な情報を知りたい方は以下の記事をご覧ください

青色申告を始める理由とおすすめ会計ソフトの選び方
青色申告は、最大65万円控除や赤字繰越といった節税メリットがあるため、副業やフリーランスには欠かせません。私の場合、サイドFIREを達成した後も副業を続けるからこそ、家計を自分でコントロールする力が必要だと考えています。だからこそ今から会計ソフトを使い、青色申告の知識とスキルを実践的に身につけておくことが大切だと思っています。
👉 この章では、青色申告の基本的なメリットと、なぜ会計ソフトを使う必要があるのか、そして私自身が青色申告を選んだ理由を紹介します。
青色申告の基本とメリット
青色申告とは、個人事業主や副業収入がある人が使える申告方法で、正しく帳簿をつけることで大きな節税メリットを受けられます。主なポイントは次のとおりです。
- 最大65万円の控除が受けられる
複式簿記で記帳し、e-Taxを使って期限内に申告すると「青色申告特別控除」として最大65万円を所得から差し引くことができます。簡易簿記の場合は10万円控除となるため、会計ソフトを利用して複式簿記に対応するのがおすすめです。 - 赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)
もし事業で赤字になった場合、その損失を翌年以降の黒字から差し引くことができます。たとえば1年目に20万円の赤字、2年目に30万円の黒字が出た場合、差し引き10万円分だけに課税されます。 - 損益通算で給与所得などと合算できる
事業所得の赤字は、給与所得や不動産所得といった他の所得と合算できます。会社員の副業でも青色申告で、節税効果が得られます。
これらのメリットを受けるには、帳簿の保存や仕訳入力が必須ですが、会計ソフトを使えば初心者でも対応できます。
会計ソフトを使うべき理由
青色申告で65万円控除を受けるためには、複式簿記での帳簿付けが必須です。しかし、仕訳を手書きやExcelで行うのは現実的ではなく、入力ミスや保存管理の手間も大きな負担になります。
その点、会計ソフトを使えば「かんたん取引入力」で支出や収入を一つずつ登録するだけで、自動的に複式簿記の形に変換されます。また、銀行口座やクレジットカードと連携して仕訳を自動化できるため、日々の記録もスムーズ。さらに、e-Taxでの電子申告に対応しているため、65万円控除を問題なく受けられるのも大きなメリットです。
つまり、初心者でも正確に帳簿をつけ、節税メリットを逃さないためには会計ソフトの導入が欠かせないといえます。
とん家が青色申告に挑戦する理由
私は簿記の初心者ですが、それでも青色申告をやるべきだと考えています。
- 家賃や光熱費を家事按分で経費化し、65万円控除とあわせて節税につなげられる
間接的に固定費を削減できるのは、資産形成期にもサイドFIRE達成後にも共通して大きなメリットです。 - ストックビジネスが育つまでは、本業との損益通算や赤字の繰越でリスクを抑えられる
初期の赤字も無駄にならず、将来の黒字や給与所得と相殺できるため、副業を安心して育てていけます。
この2つが、私が青色申告を選ぶ理由です。
青色申告で差がつく節税ワザ|家事按分・損益通算・赤字繰越

前章で簡単に紹介したように青色申告には、白色申告では受けられない節税の仕組みがあります。家賃や光熱費の一部を経費化できる「家事按分」、給与所得と相殺できる「損益通算」、赤字を3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」など、知っているかどうかで大きな差がつくポイントを具体的に紹介します。
家事按分と実例
青色申告の大きな特徴のひとつが「家事按分」です。これは、家賃や光熱費など生活と事業の両方に使っている支出を、事業に使った割合だけ経費にできる仕組みです。
たとえば自宅の家賃が10万円で、そのうち仕事用スペースとして30%を利用している場合、毎月3万円(年36万円)を経費に計上できます。光熱費やインターネット代も同じように按分でき、実質的に固定費の削減につながります。
ブログやSNS運営の場合、按分の目安は次のように考えるのが一般的です。
- 家賃・通信費:作業に使うスペースの割合(例:自宅60㎡のうち6㎡を机と仕事スペース → 10%)
- 光熱費:作業時間の割合(例:1日24時間のうち6時間を仕事に利用 → 25%)
実際の経費計上では、家賃や通信費は10%前後、光熱費は10〜20%程度を目安にしている人が多いです。
注意点として、税務署に「合理的な根拠」を説明できるかどうかがポイントです。面積比や使用時間など、客観的に示せる基準を残しておけば安心して経費化できます。
損益通算と実例
青色申告の大きな節税メリットのひとつが「損益通算」です。これは、事業で赤字が出た場合に、給与所得など他の所得と合算して税金を減らせる仕組みです。
たとえば本業の給与所得が300万円、副業で20万円の赤字が出たとします。青色申告なら
給与300万円 − 赤字20万円 = 課税所得280万円
となり、結果として所得税や住民税が軽くなります。この制度は特に「副業がまだ育っていない段階」で効果的です。収益化までに赤字が出ても、本業と合算できるため無駄にならず、安心してストック型ビジネスを育てていけます。
純損失の繰越控除と実例
青色申告のもう一つの大きなメリットが「純損失の繰越控除」です。これは、ある年に赤字(純損失)が出た場合、その赤字を翌年以降の黒字と相殺できる仕組みです。最長で3年間繰り越せるため、ストック型ビジネスの初期に赤字が出ても無駄になりません。
たとえば副業で1年目に20万円の赤字、2年目に30万円の黒字が出たとします。白色申告では2年目の30万円すべてに課税されますが、青色申告なら
30万円 − 20万円 = 10万円
が課税対象となり、大幅に節税できます。繰越控除を受けるためには、毎年の確定申告を欠かさず行う必要があります。赤字の年こそ申告をしておくことで、翌年以降の節税効果を確実に受けられます。
このように、青色申告には「家事按分で固定費を経費化」「損益通算で給与所得と相殺」「赤字を3年間繰り越し」といった節税ワザが用意されています。白色申告では受けられない仕組みばかりであり、副業を始めたばかりの段階でも将来の黒字期に向けて大きな安心につながります。
とはいえ、これらの仕組みを正しく使うためには、複式簿記による帳簿付けが必須です。ここからは、私が実際に選んだ「弥生会計オンライン」の特徴や、他社ソフトとの違いについて解説していきます。
弥生会計オンラインの評判と他社比較|マネーフォワード・freeeとの違い
| ソフト名 | 料金(目安) | 初年無料 | 操作性 | 自動化 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弥生会計 オンライン | 年10,300円 | ◎ あり | シンプル | △ 少なめ | 初年度無料で始めやすい。簿記を学びながら使える |
| マネー フォワード | 月1,280円~ | × なし | 直感的 | ◎ 強い | 銀行・クレカ自動連携に強み |
| freee | 月1,298円~ | × なし | 感覚的 | 強い | スマホアプリで手軽に入力 |
青色申告を実践するうえで欠かせないのが会計ソフトです。私はマネーフォワードとfreeeを比較検討した結果、「弥生会計オンライン」を選びました。理由は、簿記の知識が浅くても簡単に仕訳入力ができる操作性と、安心して試せる無料利用期間があったからです。ここからは、実際に使って感じた特徴を具体的に紹介します。
料金比較・初年度無料キャンペーン
会計ソフトを選ぶうえで多くの人が気にするのが料金です。私も最初に確認したのは「どのソフトがいくらかかるのか」でした。
- 弥生会計オンライン:セルフプランなら初年度無料で、2年目以降は年額10,000円前後(キャンペーン利用でさらに割引あり)。初心者がお試ししやすい点が大きな魅力です。
- マネーフォワード クラウド確定申告:月額1,280円~(年額契約で割引あり)。銀行やクレジットカード連携など、自動化機能が充実している分、料金はやや高めです。
- freee 会計:月額1,298円~(年払いでさらに割引あり)。スマホアプリやUIのわかりやすさが強みですが、安さより利便性重視の方向け。
料金だけで見ると「弥生」が一番始めやすく、特に初年度無料キャンペーンは大きな差別化ポイントです。私は「まずは試してみたい」という気持ちもあり、弥生を選びました。
操作性・自動化の違い
料金だけでなく、実際に毎日触る「使いやすさ」も大事な比較ポイントです。
- 弥生会計オンライン:取引を「かんたん取引入力」で1件ずつ登録する方式。簿記を知らなくても収入・支出を入力すれば自動で複式簿記に変換されます。自動連携機能はシンプルですが、その分「自分で確認しながら入力したい初心者」には安心感があります。
- マネーフォワード:銀行口座・クレジットカード・電子マネーなどとの自動連携が強力。仕訳も自動で提案してくれるため、データを取り込むだけで帳簿がほぼ完成します。忙しい人や自動化重視の人に向いています。
- freee:スマホアプリに力を入れており、レシート撮影や音声入力など手軽な操作性が魅力。初心者でも感覚的に使いやすい設計ですが、帳簿の裏側(複式簿記の流れ)はあまり意識できません。
私は簿記初心者として「仕訳の流れを理解したい」という思いがあったので、弥生のシンプルな入力方式が合っていました。自動化を最優先にしたいならマネーフォワード、スマホで直感的に使いたいならfreeeという違いがあります。
各会計ソフトに向いている人のタイプ別

最後に、それぞれの会計ソフトがどんな人に向いているかを整理します。
- 弥生会計オンライン
初年度無料で始めやすい。また、取引を1件ずつ入力するスタイルなので、簿記の流れを学びながら進められる。「学びながら使える」という点は、人によってはデメリット(手間)ですが、簿記知識を身につけたい人には大きなメリット。 - マネーフォワード クラウド確定申告
自動連携と仕訳提案で手間を最小限にできます。本業が忙しく、副業の経理に時間をかけたくない人や、日々の入出金が多い人に向いています。 - freee 会計
スマホアプリから直感的に操作でき、レシート撮影など手軽な入力に強みがあります。PC操作が苦手な人や、できるだけ感覚的に使いたい人に合っています。
私自身は「初期費用が安い」、「副業を育てながら簿記や会計の流れも学びたい」と考えたため、弥生を選びました。ソフト選びは「どれが一番安いか」よりも「自分のスタイルに合うか」で決めるのが正解だと思います。
弥生会計オンラインの使い方|仕訳入力・家事按分・収益処理の実例

比較を経て弥生会計オンラインを選んだ私は、実際に仕訳入力を始めてみました。複式簿記の知識が浅くても、1件ずつ収入や支出を入力すれば自動で仕訳が作成されるので、初心者でも迷いにくいのが特徴です。ここからは、私が副業ブロガーとして体験した仕訳入力の流れを、具体的な例を交えながら紹介します。
弥生オンラインの入力方式
弥生会計オンラインの大きな特徴は、複式簿記を意識せずに入力できることです。
基本は「収入」「支出」「振替」から区分を選び、日付・金額・摘要を入力するだけで、自動的に複式簿記の仕訳に変換されます。簿記の知識が浅くても、売上なら「売上高」、備品購入なら「消耗品費」といった形で選ぶだけなので、初心者でも迷いにくい設計です。
さらに、銀行口座やクレジットカードを連携すれば、自動で取引データを読み取り、仕訳候補を提案してくれる機能もあります。私は副業用クレジットカードを登録しており、経費の支払いは自動で取り込まれるので、確認して登録するだけで済むのが便利です。
つまり「最初は手入力で流れを学びたい人」も、「効率重視で自動化したい人」も、どちらの使い方もできるのが弥生会計オンラインの強みです。
家事按分や固定資産・手数料の処理(体験談ベース)
弥生会計オンラインでは、日常の支出や固定資産の扱いをスムーズに行える点が魅力です。以下に私の体験を交えながら3つの主要なポイントをご紹介します。
家事按分の活用
自宅兼事業所で家賃・光熱費などを使っている場合、「かんたん取引入力」で支払った全額を一旦入力し、決算時に事業に使った割合(例:30%など)を指定することで、自動で仕訳が作成されます。これにより、合理的に経費として処理できるので、節税効果も確実です。support.yayoi-kk.co.jp
固定資産の登録と減価償却
10万円以上のパソコンや備品などは、「固定資産の登録」画面から情報(取得価額・耐用年数など)を入力するだけで、自動的に減価償却費が計算されます。ここまで入力すれば、複雑な計算をしなくても帳簿の整理が完了するので非常に効率的です。support.yayoi-kk.co.jp+1
振込手数料の処理
A8.netなどで成果報酬を受け取る際、振込手数料が差し引かれる場合があります。弥生オンラインでは、手数料分を“支払手数料”として処理する方法が公式に紹介されています。たとえば、成果報酬33,000円から660円を差し引いた32,340円が入金された場合、以下のような仕訳になります:
普通預金 32,340 / 売掛金 33,000
支払手数料 660
このように、一括で処理できる点は非常に助かります。詳細は弥生公式FAQにも記載があります。support.yayoi-kk.co.jp
こうした機能のおかげで、家事按分も固定資産処理も負担なく行え、帳簿管理に慣れていない私でも着実に青色申告の準備が進められました。
A8.net・アドセンスの売上計上と入金処理(振込手数料含む)
副業ブロガーとして避けて通れないのが、アフィリエイトやアドセンス収益の仕訳です。弥生会計オンラインでは、売上計上と入金処理を分けて登録することで、より正確に管理できます。
A8.netの例
A8.netでは成果が確定した時点で「売掛金」として売上を計上し、実際に振込があった際に「普通預金」へ振り替える流れになります。私の場合、成果報酬33,000円から振込手数料660円が引かれ、32,340円が入金されました。
仕訳は次のようになります:
- 成果確定時:
売掛金 33,000円 / 売上高 33,000円 - 振込時:
普通預金 32,340円 / 売掛金 33,000円
支払手数料 660円 /
このように、振込手数料を「支払手数料」として分けて記録するのがポイントです。
Googleアドセンスの例
Googleアドセンスは、収益が8,000円以上になった月に翌月21日〜26日頃に自動振込される仕組みです。例えば、ある月に6,000円の収益が発生した場合、その月は支払条件を満たさないため翌月に繰り越されます。翌月にさらに2,500円の収益が加わり、累計8,500円となった時点で、翌々月にまとめて入金されます。
仕訳の流れは次の通りです。
| 発生月 | 内容 | 仕訳 |
|---|---|---|
| 7 | 収益6,000円発生 | 売掛金 6,000 / 売上高 6,000 |
| 8 | 収益2,500円発生(累計8,500円) | 売掛金 2,500 / 売上高 2,500 |
| 9 | Googleから8,500円入金 | 普通預金 8,500 / 売掛金 8,500 |
アドセンスやA8.netは「振込条件を満たさないと翌月以降に繰越」「手数料があるかないか」といった違いがあるため、仕訳の時期や入金額がASPごとに異なる点を理解しておくことが大切です。私自身も、初めて仕訳をするときはこのサイクルを確認しながら処理を進めました。
| サービス | 振込条件 | 入金時期 |
|---|---|---|
| Googleアドセンス | 8,000円以上 | 翌月21〜26日頃 (自動振込) |
| A8.net | 1,000円以上(※振込手数料あり → 公式FAQ) | 翌々月15日頃 |
| もしもアフィリエイト | 1,000円以上 | 翌々月末 |
| Amazonアソシエイト | 5,000円以上(銀行振込) | 翌々月末 |
| 楽天アフィリエイト | 1円以上(楽天キャッシュ)/3,000円以上(銀行振込) | 翌々月末 |
弥生会計オンラインでは、こうした売上や振込手数料も「かんたん取引入力」から登録できるので、簿記初心者でも迷わず処理できました。
青色申告と弥生会計オンラインのよくある質問(Q&A)
以下の疑問は、私自身も確認したポイントでした。弥生会計オンラインはこれらの処理もメニューやQ&Aから学べるので、初心者でも迷いにくいと感じています。
Q1:副業の収入で会社にバレることはある?
バレる一番の理由は「住民税」です。副業収入を確定申告すると住民税が増え、その通知が本業の会社に送られてしまう場合があります。これを避けるには、確定申告書で「住民税は自分で納付」を選択すればOKです。ただし、市区町村によっては会社に通知がいくこともあるため、事前に確認しておくと安心です。
Q2:赤字を繰り越すにはどんな手続きが必要?
青色申告をしていれば、純損失の繰越控除(最長3年)が使えます。赤字が出た年に確定申告をしておくと、翌年以降の黒字と相殺でき、税負担を軽減できます。ポイントは「赤字が出た年もしっかり申告をすること」です。
Q3:損益通算するにはどんな手続きが必要?
青色申告では、事業所得の赤字を給与所得など他の所得と相殺(損益通算)できます。確定申告書Bで給与所得と事業所得をまとめて記入すれば手続き完了です。サラリーマンの場合、給与天引きされていた所得税の一部が還付されることもあります。
Q4:セルフバックやポイント収益も計上する必要がある?
はい、セルフバックやポイントも事業の収益として計上が必要です。たとえば、A8.netでクレジットカードを発行して得たセルフバックや、ハピタスの換金ポイントは「雑収入」や「売上高」として計上します。ポイントを現金化せず生活費に使っていても、換金時点での価値を収益として扱うのが原則です。
Q5:生活費から事業に使った場合の仕訳は?
生活費を事業に使った場合は、「事業主借」で処理します。例えば、個人口座からブログのサーバー代を支払った場合:
通信費 1,000 / 事業主借 1,000
逆に、事業用口座のお金を生活費に使った場合は「事業主貸」で処理します。事業と生活をきちんと分けるための基本ルールです。
副業・フリーランスは青色申告で効率的に始めよう
青色申告は「65万円控除」「損益通算」「赤字繰越」といった大きな節税メリットがあるため、副業やフリーランスにとって必須の仕組みです。私自身も副業ブロガーとしてスタートした当初は不安がありましたが、弥生会計オンラインを導入することで仕訳や家事按分の処理がぐっとシンプルになり、安心して収益管理を進められるようになりました。
弥生会計オンラインは初年度無料キャンペーンがあり、簿記初心者でも「収入」「支出」を選んで金額を入れるだけで複式簿記に変換してくれます。さらに、銀行口座やクレジットカードと連携すれば、自動で取引を読み込んでくれるため、作業効率も大幅にアップ。
👉 もし「副業を始めたけど申告が不安」「フリーランスとして効率よく経理をしたい」と感じている方は、まずは無料で試せる弥生会計オンラインから始めてみるのがおすすめです。
【公式サイト】
関連記事リンク
- 開業届と青色申告の基礎解説|65万円控除と提出手順

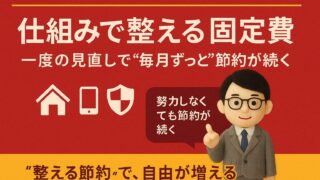
- 自分のペースでサイドFIREを目指す資産形成戦略

👉 青色申告は「節税のため」だけでなく、副業やフリーランスの活動を続けるうえでの安心の仕組み。会計ソフトを味方につけて、家計も事業も効率的に整えていきましょう。